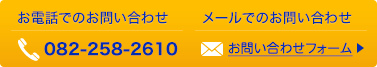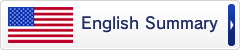NEWS&TOPICS
- 2025.08.01
- 農業革命と錦鯉飼育について-4
魚の色を生み出す色素細胞は、大きく以下の4種類に分類されます
黒色素胞(メラニン系)
黄色素胞
赤色素胞(キサンチン系)
虹色細胞(グアニン系)
これらの色素細胞が皮膚や鱗の表面に存在し外部からの光を反射・吸収することでさまざまな
色が表現されます。
黒色素胞(メラニン系)
それぞれの色素細胞は独自の役割を持ち、環境や飼料、さらには魚の健康状態に応じて変化します。
魚がストレスを感じると黒色色素胞が活性化し体色が暗くなることがあります。
この反応はストレスホルモンが影響していると考えられ環境の急激な変化や捕獲による刺激が
原因となることが多いようです。
虹色細胞(グアニン系)
水質の影響
水が清潔で透明度が高い環境では、虹色細胞が正常に発達しやすいです。
逆に汚れた水質では細胞の機能が低下し輝きが失われることがあります。
環境の安定化(水質、温度、pHなどの環境を一定に保つこと)でストレスを軽減し自然な色調を
維持します。
ルイヴィトン親会社が豊田自動織機のマシンで作られる「生地」には
工業製品に無い手作業の生地が生まれる事を研究している番組も見ましたが、日本人が知らない
そして気づかない物が多くありそうです。
これからの錦鯉業界でも日本伝統の飼育技術とAIを駆使した飼育方法に変換する時代の始まり
かもしれない。
他国では多分もうすでに始まっているだろう。
しかし日本伝統の飼育技術にはおいそれとは追いつけないだろう。
何故なら日本人特有のこだわりと感性があるので・・・。
しかし「水質」の事は基本中の基本なのでもう少し知識を増やしていかないと
日本の錦鯉の将来は・・・・?